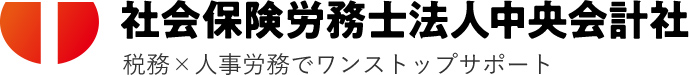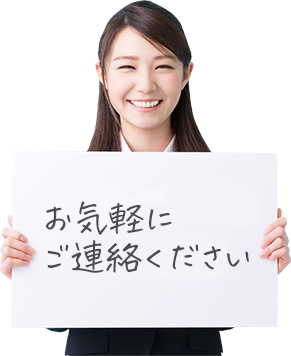社会保険と税法上の「扶養」は何が違う?
専門家でも混乱する“壁の違い”を、中央会計社がわかりやすく解説!
こんにちは。社会保険労務士法人中央会計社です。
近頃、企業様から次のようなご相談をいただくことが増えています。
- 103万円と130万円、どっちの壁を説明すればいいの?
- 税理士からは103万円と言われるのに、社労士からは130万円と言われる…
- 従業員に“扶養が外れる”と言われたけど、どの扶養のこと?
実はこの混乱、“扶養”という同じ言葉が2つの制度で全く違う意味を持っているために起きています。
また、令和7年の税制改正により「税法上の壁」の金額が変わったため、さらに注意が必要です。
まずこの違いをしっかり押さえていきましょう。
1. 扶養には「社会保険」と「税法」の2種類がある
同じ“扶養”でも、
- 社会保険の扶養(健康保険・年金)
- 税法上の扶養(所得税・住民税)
は全く別の制度です。
この2つを混同すると、
『壁を超えるとどうなるのか』 『本当に扶養から外れるのか』
が分からなくなります。
ここからはとくに混乱しやすい 社会保険の扶養をしっかり解説し、
税法上の扶養は令和7年の最新情報を簡潔にまとめていきます。
2. 社会保険上の扶養の考え方(ここが一番大事!)
社会保険の扶養は、
健康保険・年金の保険料を払わずに加入できる制度です。
会社として従業員に説明する際も、
実務ではこの「社会保険の扶養」が最も重要になってきます。
① 基本は “年収130万円未満” が基準
社会保険の扶養では、
被扶養者の年間収入が130万円未満
というのが最も中心となるラインです。
- 130万円未満⇒被扶養者として加入OK
- 130万円以上⇒扶養から外れて本人が社会保険料を負担
これがいわゆる 「130万円の壁」 です。
② ただし短時間労働者は“106万円の壁”もある
勤務先が一定規模以上の場合(社会保険適用拡大)、
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)
- 2か月超の雇用見込み
- 学生ではない
などの要件に該当すると、年収106万円付近で加入が必要になるケースがあります。
ここは企業側が誤解しやすいポイントです。
③ 2025年10月からは“150万円の壁”が誕生
2025年10月からは社会保険の扶養基準にも新たな動きがあります。
- 19歳以上23歳未満の学生の場合、健康保険の扶養から外れる基準が年収130万円から150万円に引き上げられました。
これは、将来を担う学生のアルバイト収入が社会保険の壁を気にせずに済むように設けられた特例です。
④ 同居と別居で条件が変わる(非常に重要)
社会保険の扶養認定は、
“その人の生活を誰が支えているか” を重視します。
✔ 同居の場合
収入要件(130万円未満)を満たせばOK。
生計維持関係は認められやすいです。
ただし、扶養される方の収入は扶養する方の1/2未満である必要があります。こちらもお忘れなく♪
✔ 別居の場合
別居している場合は“仕送り”が必要です。
- 被保険者(夫・親など)が生活費の主な負担者であること
- 仕送り額が生活費の中心となっていること
- 送金記録などの証明が必要
が求められます。
ただし、扶養される方の収入は仕送り額よりも少ないことが条件になります。こちらもお忘れなく♪
⑤ ポイントまとめ(社会保険)
- 社会保険の扶養は「130万円」「106万円」が中心
- 2025年10月より学生特例として「150万円」の壁が登場
- 税法上とは全く別の制度
- 同居・別居で判断が変わる
- 収入基準を1円でも超えると扶養の扱いが変わる場合がある
3. 税法上の扶養の考え方(令和7年最新ポイント)
税法上の扶養は、
税金を計算するときに控除(税金を安くする)が受けられるかどうかという制度で、社会保険とは別です。
令和7年分の確定申告・年末調整からは、以下の新しい基準が適用されます。
① 配偶者(妻・夫)の場合(⇐基準が変更されました!)
給与所得者の基礎控除と給与所得控除の引き上げにより、配偶者控除・特別控除の基準となる「壁」が変更されました。
| 旧基準(令和6年分まで)
|
新基準(令和7年分から)
|
意味合い
|
||
|
103万円の壁
|
123万円の壁 | 配偶者控除の満額(38万円など)を受けられる給与収入のライン(所得税が非課税となるライン) | ||
|
150万円の壁
|
160万円の壁 | 配偶者特別控除の満額(38万円)を受けられる給与収入のライン | ||
|
201.6万円の壁
|
201.6万円の壁 | 控除ゼロとなるライン(変更なし) |
税金上は壁が細かいですが、扶養から“外れる・外れない”というより、控除額が変化する仕組みという原則は変わりません。
子・親・祖父母など(控除対象扶養親族)
- 年齢16歳以上
- 所得58万円以下(給与収入123万円以下)【←所得の基準が変更されました!】
- 生計を一にしていること
こちらも”基礎控除の引き上げ(48万円→58万円)”に伴い、所得の基準が変更されています。
4. なぜ社労士と税理士で説明が違うの?
理由はとてもシンプル。
● 社労士 ⇒ 社会保険の扶養(130万円/106万円)で説明する
● 税理士 →⇒税法上の扶養(123万円/160万円/201.6万円)で説明する
どちらも正しいのに、制度が違うので聞き手が混乱してしまうのです。
よくある「扶養から外れるらしい」「壁を超えたら損らしい」という相談も、制度を混ぜて考えてしまっているケースが大半です。
中央会計社なら“両方の制度”をまとめて説明できます!
中央会計社には社会保険労務士法人と税理士法人の両方がそろっています。
だからこそ、
- 社会保険と税法の扶養の違い
- どの壁が会社に影響するのか
- 従業員へどう説明すべきか
- 年末の働き方調整をどう案内するか
すべて一体としてアドバイスできます。
迷ったらぜひご相談ください!
最新のお知らせ・セミナー情報